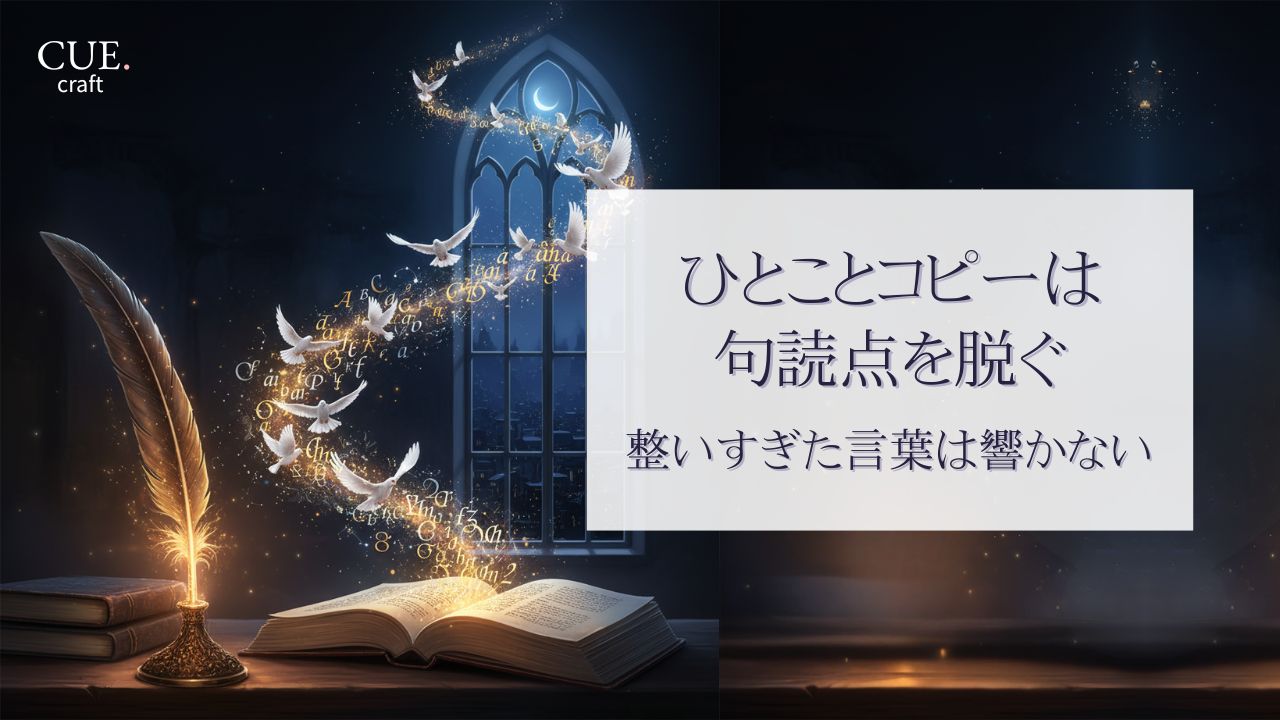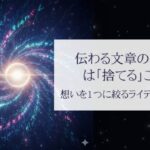【今日のひとこと】
伝えることが上手になった時代に——
いちばん響くのは上手じゃない言葉だ
子供を寝かしつけと夜の家事を終え、やっと仕事ができると向かった深夜のダイニングテーブル。
なかなかに心地よいリズムのキャッチコピーが、画面の上で静かに光っている。
言葉は、美しい(はず)。ロジックも、通っている(はず)。
クライアントはきっと、これを褒めてくれるだろうと、一人ほくそ笑む。
——なのに、何かが足りない。
なんだ?なんだ?何なんだ??
書き手である自分自身の心が、少しも動いていないのです。
いつからだろう。言葉を「書く」ことが、心を「動かす」ことではなく、ただ言葉を「整える」作業になってしまったのは…
これは、そんな夜を過ごしたことのある、あなたに贈るコラムです。
突然ですが、最近こんなコピーを見かけませんか?
自分らしく、軽やかに。
明日を、もっと美しく。
*私がいま、例として作りました。もし既にあるコピーだったらごめんなさい。
短いセンテンスの中に「、」と「。」を巧みに配置する、「〇〇、〇〇〇。」の形。
まるで日本語の呼吸そのものをデザインしたような、美しいリズム。
強さと余韻。凛とした品と、やさしい距離感。
この型は、本当に完成度が高いと思います。
私自身も、ここ数年よく使ってきました。句読点は、感情の温度をコントロールできる、転生アニメの勇者もびっくりの”チートツール”だとさえ思っていたからです。
——でも、最近、少し飽きてきてませんか?
映画の予告も、電車の中吊り広告も、通販カタログの表紙も。
いまや「キャッチコピーといえばこのリズム」と言えるほど、あらゆる場面で目にします。
もちろん、大切なのは言葉の意味であり、そこから生まれる世界観こそが本質です。
多様されるということは、それだけ反応が取れるということでもあるでしょう。
でも、最近では意味より先に、目が「またこの型か…」と反応してしまう自分がいます。
この違和感は、何だろうか。考えていくうちに、こう思うようになりました。
整いすぎたコピーが行き着くのは、“感情の無風状態”なのではないか、と。
なぜ「、」と「。」のリズムは、これほどまでに心地よいのか
そもそも、なぜ私たちは句読点が入ったリズムに惹きつけられるのでしょう。その理由は、日本語が持つ構造と、私たちの脳の仕組みに隠されていました。
理由1:身体に染みついた「日本語の呼吸」だから
言うまでもなく、句読点は日本語の基本。小学校の音読の授業でも「、」で息継ぎをして、「。」で心の中で拍をとるように教わりました。
私たちは子どもの頃から、「句読点があったら、余韻をつくりましょう」と身体で学んできたのです。その感覚は大人になっても無意識に息づいており、「、」と「。」を目にした瞬間、私たちの脳は自然と呼吸を整え、言葉の余韻を感じ取ります。
この慣れ親しんだ“日本語の呼吸”は、それだけで大きな安心感と心地よいリズムを生み出すのです。
理由2:脳に“思考の余白”を与えてくれるから
もうひとつの理由は、句読点が脳の中に思考の余白をつくってくれるからです。
現代人が1日に触れる情報量は、江戸時代の一年分とも言われます。常に“情報の洪水”にさらされる中で、句読点は脳の整理役を担ってくれます。
「、」で文章を区切り、「。」で「はい、ここまで」と記憶を整理する。そして、その一瞬の静止の間に、読み手の脳内では映像が立ち上がります。句読点が入るたびに、思考のピントが合うような感覚です。これは、多くの書き手が実感するところではないでしょうか。
理由3:日本語特有の「感情を伝える“間”」
英語のピリオドやカンマが、主に文法や論理を整える記号であるのに対し、日本語の句読点は“感情の設計”そのものです。
かっこよく言うならば、
「、」が生まれると、言葉に息が宿る。
「。」が打たれると、心に光が残る。
こんな感覚。
たった一つの記号が、情景を浮かび上がらせ、感情を動かすのですから、不思議ですね。句読点は、意味を伝えるための道具ではなく、心を伝えるための間(ま)なんです。
完璧なリズムが生んだ副作用。なぜ言葉は体温を失ったのか
句読点が織りなす詩的リズムが、あまりにも完成されてしまったからこそ、いま、言葉が少し冷えてしまったように感じます。
誰もが心地よく、上手に、綺麗に書けるようになった。けれど、同じリズム、同じ余白、同じやさしさが並ぶと、そこに「個の体温」が薄れていくような感覚を覚えます。
「うまく書けている」のに、なぜか心が動かない。それは、句読点という完璧なリズムの中に、「揺らぎ」や「ノイズ」がなくなったからかもしれません。
本来、呼吸のためにあったはずの「、」や「。」が、いつしか言葉を”整える”ための記号になってしまった。それはまるで、人の息づかいをオートチューンで加工したような感覚。美しいけれど、どこか無機質で、温度が感じられないというか…。
言葉って、本来はもう少し、ざらっとしていていい。 にごりや、迷い、戸惑いも、全部ひっくるめて“人間の声”なんだと思ったりもしています。
「整える」から「揺らす」へ。共感を呼ぶコピーの新潮流
句読点の時代を経て、次に私たちが目指すべきは、整った言葉のその先。完璧なやさしさではなく、すこし乱れた呼吸の中にある「ほんとうの温度」です。
いま、コピーは少しずつ、「人間」を語り始めています。
完璧に整った言葉よりも、どこか欠けている言葉。 美しい理屈よりも、少し不器用な感情。
そんなにごりや迷いの中にこそ、いまの時代のリアルが宿っています。 「弱さ」は、共鳴のはじまりで、「揺らぎ」は、呼吸の証とでもいいましょうか。
AIが普及し、美しい言葉はだれでも簡単につくることができるようになりました。だからこそ、私たち人間は、人間だからこそかける心のゆらぎであり、荒削りな感情を表現していくことが、AIとの差別化になるのではないかと思います。
きれいに整えることが、必ずしも“伝わる”ことではない。 むしろ、これからのコピーに必要なのは、ザラッとした生活から滲み出る言葉なのではないでしょうか。
完成された言葉を見せるのではなく、言葉が生まれる「生成」のプロセスを見せ、読者が「共に感じる」余白を持つ言葉が、心を動かしていくのだと思います。
新しい文体の地平へ。これからの時代を動かす5つの“体温のある文体”
では、今後はどのような文体が流行っていくのか、少し考えてみました。(個人的に考えたものなので、本当に流行るかはわかりませんよ。笑)
これからのコピーに名乗りを上げてくると考えているのは、まるで呼吸をするように、人間の揺らぎをそのまま記すスタイルです。
呼吸詩型(こきゅうしがた)
息づかいで書く。読者の呼吸とリズムを共有し、句読点の“間”で感情を語る。
ざらつき型
未処理の感情を残す。削がず、磨かず、心のノイズをそのまま表現する。
錯覚文型
感覚で伝える。理屈よりも“見える”“聞こえる”“触れる”を優先する。
囁き体(ささやきたい)
心の声の距離感で書く。断定せず、語りかけの呼吸で、感情をそっと渡す。
余熱文型(よねつぶんけい)
言葉のあとに残す。読み終えた後の静けさに、感情の余韻を置いていく。
これらは、「整えるための文体」ではありません。書き終えたあとに残るのは、正確な意味ではなく、感情の残り香。ちょっとカッコよくないですか?これこそ、余韻!
おわりに|言葉の未来へ、私たちが取り戻すべきもの
コピーの役割は、モノを売ることでも、メッセージを伝えることでもないのかもしれません。
もちろん、私たちの仕事は、モノやサービスを売るためにあります。
でも、真髄は、人と人のあいだに、呼吸を取り戻すこと。
そして、お届けしたい人の生活の中でモノやサービスが生き生きと輝くこと。
整いすぎた言葉の中で失われた、体温や、にごりや、迷いこそが、生活そのものなのではないかと思うのです。
ガサガサした感情をもう一度、言葉の中に帰していきたい。完璧じゃなくて、むしろ、未完成のままの方が届くのかもしれないと思っています。
書き手の呼吸がそのまま届くこと。
それが、これからの時代にいちばん必要な伝わり方なのだと感じる、今日この頃です。
伝えることが上手になった時代に——
いちばん響くのは上手じゃない言葉だ